海外の研究からみた、イヤイヤ期の原因と軽減するポイント

イヤイヤ期について、ネットで調べてみると、「大変、きつい」という情報や、「~したらよいですよ」といったアドバイスなど、さまざまな情報が出てきますね。
今回の私の記事は2018年の海外の研究で明らかにされた、イヤイヤ期が起こる原因の紹介と、それを踏まえた上で、イヤイヤ期と反抗期を軽減するために、遊びの重要性について紹介していきます。
↓今回の内容
- イヤイヤ期の原因は「言葉を伝えられない、言葉に表せないことへのイライラ」
- イヤイヤ期は一緒に遊んで、子どもともっとつながろう
- イヤイヤ期を抑制するには、言葉を育てよう
イヤイヤ期の原因は「言葉を伝えられない、言葉に表せないことへのイライラ」

イヤイヤ期がなぜ起こるのか、その原因を一言でいうと「子どもは言いたいことがあるけれど、言葉に表せないことでイライラするから」です。
2歳前後は言葉を多く話せるようになってきますし、「自分でできる」という思いを強く持つ時期になります。
この時期になると、「自分は出来るはずなのに、なんて言ったらいいか分からない」や「自分は言っているのに、家族の人が分かってくれない」といった言葉が原因となるストレスを子どもが抱えていきます。
そのストレスが溜まっていくとイヤイヤ期の代名詞とも言える、叫ぶ、泣く、暴れるといった行動につがなっていくのです。
要するに、言葉の発達が遅い子どもほど、イヤイヤ期の影響が大きくなりやすいと言うことができます。
イヤイヤ期は一緒に遊んで、子どもともっとつながろう

では、イヤイヤ期の時に子どもに話を聞いてもらう方法についてですが、ここで紹介するのは、子どもに好かれること、要するに一緒に遊びましょうということです。
遊びは、子どもと親とをつなぐ良い方法だと説明されています。
一緒に遊ぶことで、お互いの理解が進み、相手を好きになる。
すると、相手が好きな人だと、相手のことを考えた行動をとることができ、精神的に落ち着くことができると研究においても説明されています。
確かに、私の娘も妻よりも私の方が話を聞いてくれているような気もします。
休みの日によく散歩に連れて行ったのが良かったのでしょうね。
(嫁さんへ。気のせいだったら、ごめんよ)
言葉を意識するのであれば、いつも一緒にする遊びに加えて、ごっこ遊び、おままごと等を加えてみてもよいでしょう。
ごっこ遊びやおままごとでは、お風呂の場面、ご飯の場面など、さまざまな場面の言葉を使う練習ができるかもしれませんね。
イヤイヤ期を抑制するには、言葉を育てよう
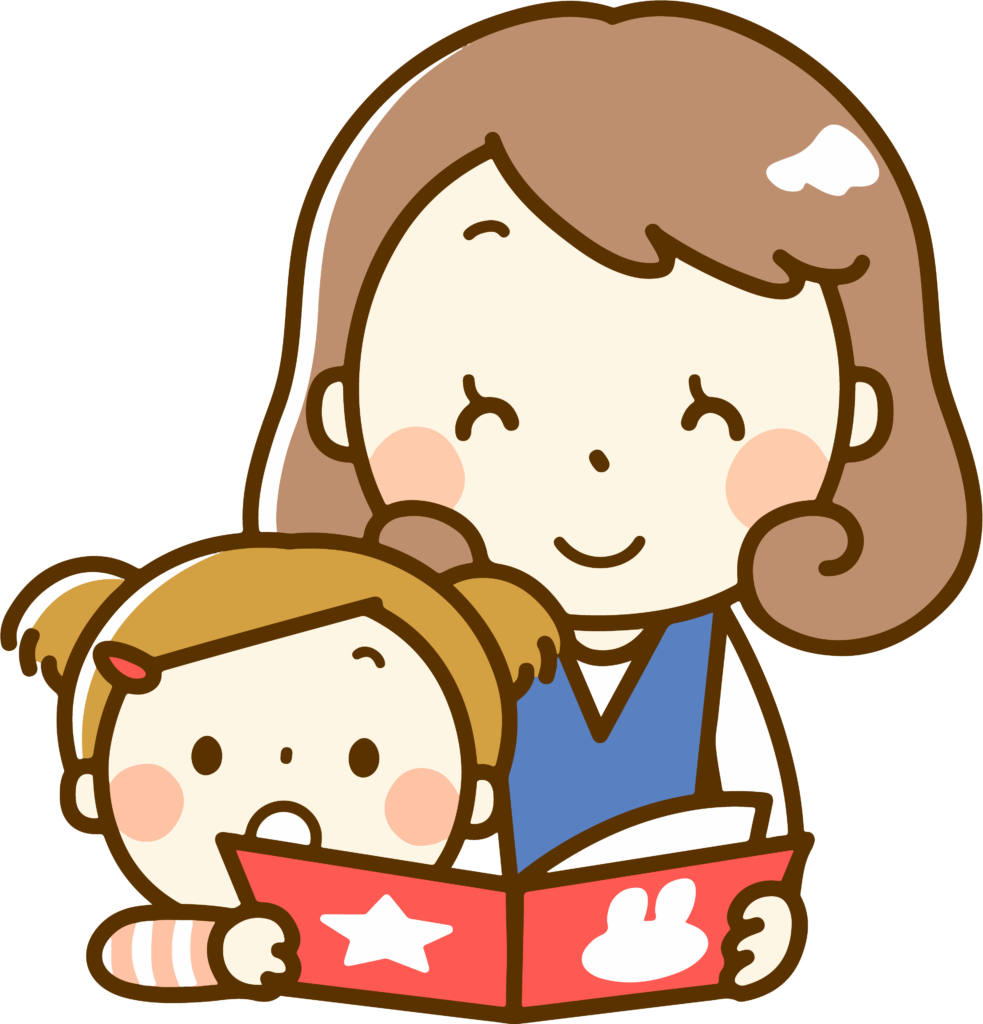
研究では1歳半~3歳までに言葉を育てていけば、イヤイヤ期、そしてこれからの反抗期での激しい行動が少なくなっていくと書かれてありますので、可能な限り早い段階から、言葉に触れさせていくことが必要なようです。
言葉に触れさせる方法として、どのような方法があるでしょうか。
先ほど述べた、ごっこ遊びやおままごとだけではなく、親同士の会話や親子の会話を大切にするのが最も大切だと思います。
他には、子どもの不安やイライラを聞いて、親が代わりに言葉にしてあげて、子どもに表現の仕方を教えてあげる、というのも一つの手ですね。
または、0歳の頃から本を読み聞かせしてあげるのもよいかもしれませんね。
終わりに
今回の記事はいかがだったでしょうか。
イヤイヤ期のお子さんを育てるのはとても大変です。
「もういや!」と投げ出したくなることも沢山あるかと思います。
しかし、イヤイヤ期はお子さんが成長する上で大切な時期でもあります。
・遊びを通して、子どもとの関係をよいものにしていく
・言葉に触れさせて、言葉が育つように工夫する
この二点に意識を向けて、イヤイヤ期のお子さんに関わってみて下さいね。
参考論文
- Joan Raphael-Leff (2012) “Terrible Twos” and “Terrible Teens”: The Importance of Play, Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 11:4, 299-315
- Megan Roberts;Philip Curtis;Ryne Estabrook;Elizabeth Norton;Matthew Davis;James Burns;Margaret Briggs-Gowan;Amelie Petitclerc;Lauren Wakschlag; (2018) Talking Tots and the Terrible Twos: Early Language and Disruptive Behavior in Toddlers, Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 39(9):709–714
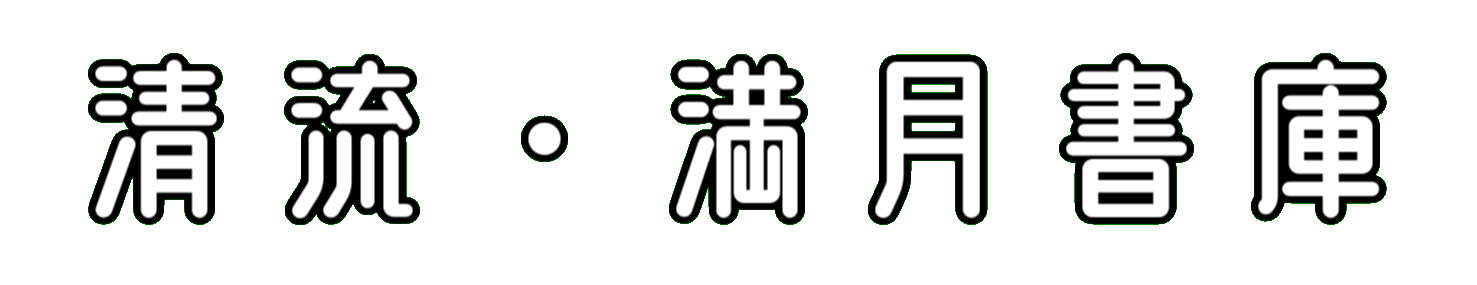







コメント