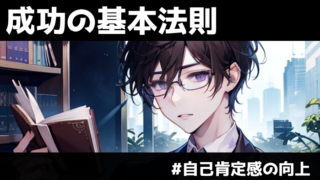 成功哲学
成功哲学 自分を認め、好きになる方法。自分嫌いを治すには、これらのシンプルな方法が有効です。【成功哲学】
自分を変えたい、成長し続けたい、目標を達成したい、そんな願望をお持ちの皆さん。ようこそ、本ブログへ。 このブログでは、様々な成長や成功に関する本を読み漁り、実践して効果があると実感したものについて、お伝えしていきます。 本ブログを通して、成...
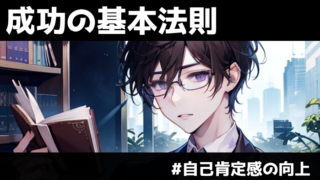 成功哲学
成功哲学 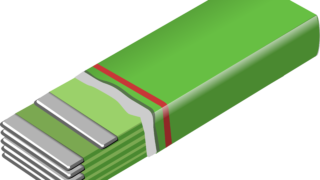 知識 ~knowledge~
知識 ~knowledge~  成功哲学
成功哲学  成功哲学
成功哲学  成功哲学
成功哲学 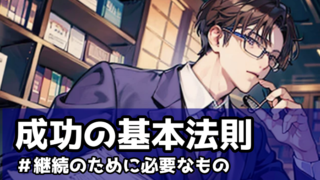 成功哲学
成功哲学 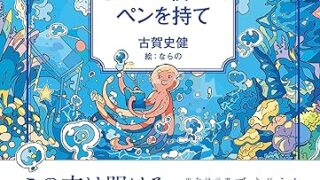 読書記録と要約
読書記録と要約 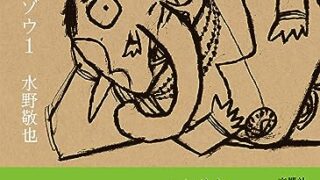 読書記録と要約
読書記録と要約 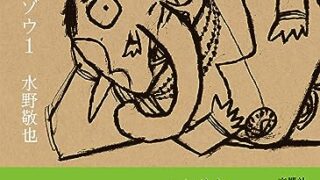 読書記録と要約
読書記録と要約 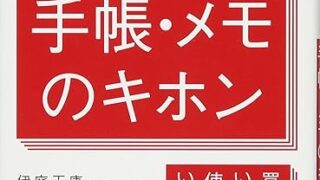 読書記録と要約
読書記録と要約 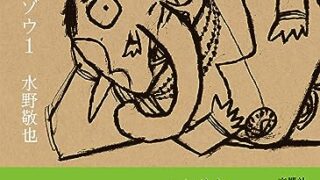 読書記録と要約
読書記録と要約  読書記録と要約
読書記録と要約 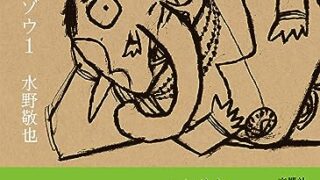 読書記録と要約
読書記録と要約  読書記録と要約
読書記録と要約  読書記録と要約
読書記録と要約